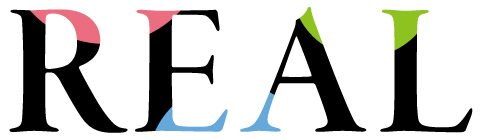近年の医療の進歩によってあらゆる疾患の予後は著しく改善したが、それに伴い医療費は急激な高騰をきたした。結果、本邦の医療財政は高齢化社会への移行とも相まって逼迫した状態となっていることは周知の事実である。高騰した医療費は世界的に共通の問題であり、マサチューセッツ州ケンブリッジにある医療改善研究所(IHI)の社長兼最高経営責任者であるドナルド・バーウィックらは2008年にTriple aimの概念を提唱した。現在、このフレームワークは米国における医療政策に広く応用されている。医療制度の改善には3つの目標を同時に追求する必要があるという提案である。
- 医療の質を高める
- 健康増進を促進させる
- 医療コストを低下させる
この3つの目標は独立したものではなく相互依存関係にあり、1つの目標を追求すると他の2つの目標に影響を与えることになる。 例えば、新しく効果的で高価な技術や薬物の導入は医療コスト上昇につながるが、診断の誤りや治療の過剰を防ぎコストの削減と結果の改善につながりえる。このように、相矛盾する面を有しており、鼎立させるのは難しい目標といえる。一方、それを実行する企業、病院は利益を追求する立場にある。 公共の利益と個人の利益が対立しがちであるといった現実は、昨今の医療政策が我々の目にnegativeに映る。そのような中、アカデミア自らtriple aimを具現化しようとしたのが、近年の米国におけるappropriate use criteria(AUC)である。本来、AUCは施設の均霑化、成績の向上を目指した概念であったが、保険の支払いにも利用されたため当初大きな批判を受けた。 しかし、あきらめることなく改定を重ね今では基本的な考えとして定着している。
CVITでは学会のオウトノミーとしてフィードバックシステムを三年前に導入し、適正化の方向に舵をきった。米国と同じ潮流といえるが、評価という点で大きく異なる。適正な医療を病院内外で評価する仕組みが米国にはあるが、本邦ではあくまでもオウトノミーとしての自己努力にとどまり収益には還元されない。この動きは行政には一定の評価を得ているようであるが、形になって見えればさらに推進されるだろう。 3つの目標はある意味、パラドックスであるため3方向がwin winとなるのは難しいことは語るまでもない。 最近の新たなデバイス承認は限られた適応、施設基準、適正使用などが必ずついてくるが、これもtriple aimの一つの形と考えることができる。 しかし、そこに留まることなく、適応を拡大し、施設を拡大していく必要がある。そのためには、産官学でお互いを理解し、議論すること、そしてチャレンジすることが必須である。逆に、これ以外によい方法はないと思う。 他の国とは環境が異なり本邦は国民皆保険で優れた医療システムで運用されている。この医療システムを維持するためにもtriple aimを前向きに捉え追及しなくてはならないと考える。バランスのとれたトリプルエイムを、次世代につなぐためにも。